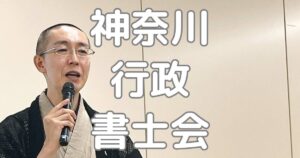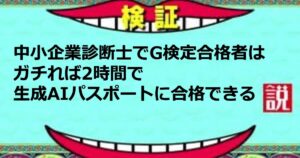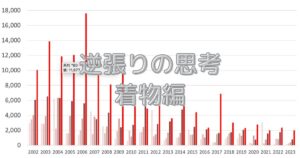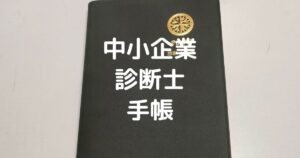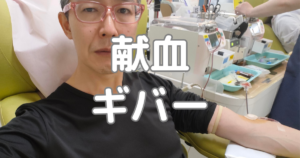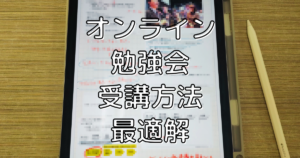こんちには。今日は私が最近感銘を受けた田坂広志氏の著書「なぜ、我々はマネジメントの道を歩むのか」を元に、マネジメントについて考えてみました。
経営者が背負う「重荷」の本質
本の冒頭では、田坂氏はマネジメントの道を歩む人々に対して、「なぜ、あなたは、自ら「重荷」を背負うのか」と問いかけます。この「重荷」とは、売上や収益といったような、定量的な数字ではありません。
本当に背負うべき「重荷」。それは、部下や社員の人生です。
社員の生活に責任を持つことに加え、私たちは、その社員が「成長」することに責任を持たなければならないのです。社員はいつか組織を巣立つ日が来ます。その後の人生を自らの力で支えていけるよう、私たちが預かる期間に「職業人としての成長」や「人間としての成長」を支える責任があるのです。
重荷こそが成長
かつてマネジメントの立場に立ちたくなかったと語る著者自身が、最終的にその道を歩んだ理由は、「一人の人間として成長できるから」という逆説的な結論でした。
部下の人生を預かるという「重荷」があるからこそ、困難に直面した時でも、「この部下のためにも、ここで挫けるわけにはいかない」と考えることで、自らの内から大きな力が湧いて、人間として大きく成長できるのです。
マネジメントの究極は「心のマネジメント」
この「重荷」を背負い、部下の成長を支えることの難しさは、正解がないことにあります。部下の性格や状況、心境、力量など、様々な要素を深く考え、その場その場で判断を誤れば、逆に成長を損なうこともあるからです。
そこで求められるのが、マネジメントの究極の世界「心のマネジメント」です。
具体的には、仏教の「対機説法(相手の機に応じて語る)」の思想に象徴されるように、部下一人ひとりの「機」、つまり、その時の状況や心境を深く理解し、最も適切な言葉で指導する力が求められます。これは、相手の心のリズムや動きを感じ取る「リズム感」と「バランス感覚」といった「心の力」を磨くことによって可能になります。
人間としての成長
田坂氏は、「人間としての成長」の定義はただ一つ、「心の世界が見えるようになること」であると述べています。
「心の世界」とは、以下の三つを指します:
- 「相手の心」:無言の声が聞こえる力
- 「集団の心」:場の空気や雰囲気を皮膚感覚で掴む力
- 「自分の心」:最も見えにくい「無意識の世界」に気づく力
特に「自分の心」が見えることは、マネジャーが部下の成長を妨げる「深い劣等感」といった無意識の「コンプレックス」に気づき、それを抑圧せずに認めることで、部下の心を殺さずに済む「救い」につながります。
最高の人間観と奇跡の出会い
マネジャーが身につけるべきは、書物から知識として学ぶ「人間学」ではなく、生身の人間と正対して体験する「人間観」です。
そして、その「人間観」の先に、著者が到達した最も深い答えがあります。それは、我々がマネジメントの道を歩む理由のもう一つの答え、「人間との邂逅(めぐりあい)」です。
職場での「出会い」は、単なる偶然ではなく、深い縁からの巡り会いです。部下という一人の人間との出会いは、六五億の人々の中で互いに巡り会った奇跡の一瞬なのです。
この奇跡的な出会いを、互いの成長を通じて最高の一瞬にして、人間同士の深い交わりの中で「最高のアート」を創り出すこと。それが、マネジャーが残し得る、いかなる事業や名声よりも素晴らしい「最高の作品」であるというのです。
最後に
「マネジャーとは、部下や社員の人生を預かる」という重荷を背負い、悪戦苦闘する道です。しかし、その重荷を背負い、目の前の社員一人ひとりと真摯に向き合うことこそが、経営者やリーダー自身を人間として最も大きく成長させる道になります。
おかげさまで最近は色んな方にお会いする機会が増えて、一緒にお仕事をさせていただくことがあります。私がお会いする方々は経営者の方が多いので、上司と部下の関係ではありませんが、この巡り合いを大切にして、互いに成長していきたいなと思います。